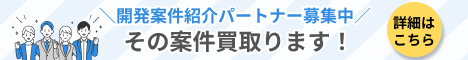最終更新日:2024/08/29
ビジネスモデルとは|事業の設計図
ビジネスモデルとは「企業が事業を通じて顧客に価値を提供し、収益を生み出す仕組み」のことです。企業なら必ず何らかのビジネスモデルをもとに経営活動を行っています。
ビジネスのあり方は時代の流れで変化していくものです。ビジネスモデルも定期的に見直す必要があるでしょう。本テキストではビジネスモデルの構成要素や設計のフレームワーク、構築のポイントやビジネスモデルの種類・事例について詳しく解説します。
ビジネスモデルの4つの構成要素
ビジネスモデルは、主に以下の4つの構成要素から成り立っています。
- Who(誰に)
- What(何を)
- How(どのように)
- Why(なぜ)
『誰に対して』『何を』『どのように価値を届け』『どう収益を上げるのか』の4つをまとめることで、ビジネスモデルを設計することができます。
それぞれの要素について簡潔に解説します。
Who(誰に):ターゲット顧客の特定
構成要素の1つめ『Who(誰に)』では、『ターゲット顧客の特定』を行います。既存顧客の分析と潜在顧客の想定が必要です。どのような顧客に価値を提供するのかを明確にし、顧客のニーズ、課題、購買行動などを分析します。
What(何を):提供する価値の明確化
構成要素の2つめは『What(何を)』です。顧客にどのような価値を提供するのかを具体的に定義し、商品、サービス、コンテンツなど、提供する価値を明確にします。
顧客に提供できる新しい価値に加え、顧客の不満を解消する方法についても考えましょう。
How(どのように):価値を届ける方法
構成要素の3つめである『How(どのように)』では、顧客に価値を届ける方法を明確にし、集客方法、販売チャネル、価格設定、顧客サポートなどを検討します。
Why(なぜ):収益の仕組みと利益の源泉
最後の構成要素は『Why(なぜ)』です。どのように収益を上げ、利益を生み出すのかを考え、収益構造、コスト構造、競争優位性などを分析します。料金や価格の設定についても今一度見直します。
ビジネスモデル設計のフレームワーク
ビジネスの構造を可視化した『ビジネスモデルキャンバス』というフレームワークがあります。これはスイスのビジネス理論家で起業家のアレクサンダー・オスターワルダー氏が2005年に提案したもので、ビジネスモデル全体を俯瞰的に把握できるため、新しいビジネスモデルを開発したり、既存のビジネスモデルを文書化したりするために使われるものです。
ビジネスモデルキャンバスは9つの要素からなる設計テンプレートです。この項ではビジネスモデルキャンバスの9つの構成要素について解説します。
ビジネスモデルキャンバスの9つの要素
ビジネスモデルキャンバスの9つの要素は以下の通りです。
- 顧客セグメント(Customer Segments)
: どのような顧客グループに価値を提供するのか
- 価値の提案(Value Propositions)
: 顧客にどのような価値を提供するのか
- チャネル(Channels)
: 顧客にどのように価値を届けるのか
- 顧客との関係(Customer Relationships)
: 顧客とどのような関係を築くのか
- 収益の流れ(Revenue Streams)
: どのように収益を上げるのか
- コスト構造(Cost Structure)
: 事業を運営するために必要なコストがどれくらいかかるのか
- 主要な活動(Key Activities)
: 価値を提供するために必要な活動と、リソースの強化や創出に必要な活動
- 主要なリソース(Key Resources)
: 事業を運営するために必要なリソースがどれくらいかかるのか
- 主要なパートナー(Key Partnerships)
: 事業を運営するために必要なパートナーの数や種類
これらをキャンバスにまとめていくことで、ビジネスモデルの姿を俯瞰で見ることができ、強みや弱みなどもよりわかりやすくなります。
Strategyzer社のサイトには、無料でビジネスモデルキャンバスのテンプレートが公開されています。
https://www.strategyzer.com/library/the-business-model-canvas
ビジネスモデル構築のステップとポイント
ビジネスモデルを構築するには、いくつかのポイントがありますが、市場調査と競合分析を行って自社の強みとリソースを把握し、テストと検証、改善を行うというのが基本の流れです。
市場調査と競合分析
どんな市場を選んでも競合となり得る企業は存在しますし、どんな市場においてもターゲットやニーズの分析は必要不可欠です。
市場調査と競合分析においては、主に下記の2点が重要です。
- ターゲット市場を調査し、顧客ニーズや競合環境を分析する
- 自社の強みや差別化ポイントを明確にする
市場と競合だけ調査・分析して終わり、ではなく、自社の強みや差別化できるポイントを明確にします。また、調査を行う際にはどのような目的で調査を行い、調査結果を何に役立てるのかを具体的にしておきましょう。
自社の強みと資源の把握
調査や分析においてもある程度は自社の強みや市場でのポジションが見えてきますが、改めてこの段階で他社と比較した上での自社の強みとリソースを把握しておきます。下記の2点がポイントです。
- 自社が持つ強みやリソースを洗い出す
- 競合との差別化ポイントを明確にする
自社の強みを知るための分析にはさまざまな分析手法が存在しますが、ビジネスモデルを評価するにはVRIO分析が役立ちます。
VRIO分析
VRIO分析とは、以下の4つの要素の頭文字を取った分析手法です。
- Value(経済的価値): 経営資源がもたらす経済的な価値
- Rarity(希少性): 経営資源の希少性
- Imitability(模倣可能性): 経営資源の模倣可能性
- Organization(組織): 経営資源を活用する組織的能力
経営資源を洗い出し、上記の4つの要素について、必ず上記の通りの順番に評価を行います。「その経営資源には『Value(経済的価値): 経営資源がもたらす経済的な価値』があるか?」の問いにYESと答えられるなら次の『Rarity(希少性): 経営資源の希少性』について評価します。
そのようにして4つの評価をクリアできれば、競争優位性のレベルは最大ということになります。
仮説検証と修正
ビジネスモデルの構築ができたら、いよいよ仮説を立てて実際に検証を行っていきましょう。その結果に応じて柔軟に修正を繰り返します。この段階では下記の2点が重要です。
- 仮説を立てて検証し、必要に応じて修正していく
- 顧客からのフィードバックなども取り入れ、柔軟に事業を修正していく
店舗ビジネスであればプレオープンなどを活用して仮説の検証と修正を行うのが一般的です。このような修正を『ピボット』と呼ぶことがあります。
ピボットとは
ビジネスにおいて『ピボット』とは、当初の事業計画やビジネスモデルを変更し、新しい方向へと舵を切ることを言います。
市場環境の変化や顧客ニーズの把握、競合分析などを踏まえ、より成功の可能性が高い事業へと方向転換を図るものであり、ビジネス戦略の一種です。
ピボットは主に下記の4種類に分けられます。
- 顧客ピボット: ターゲット顧客の変更
- 商品・サービスピボット: 商品・サービス内容の変更
- チャネルピボット: 商品・サービス提供方法の変更
- ビジネスモデルピボット: 収益構造や事業モデルの変更
代表的なビジネスモデルの種類と事例
世の中にはさまざまなビジネスモデルが存在しており、全てをご紹介することはできません。この項では、近年一般的となった『サブスクリプションモデル』『フリーミアムモデル』の2つのビジネスモデルを解説します。
サブスクリプションモデル
『サブスク』という略称でも親しまれるほど一般的になったビジネスモデル『サブスクリプションモデル』は顧客が定期的に料金を支払うことで商品やサービスを利用できるビジネスモデルです。利益を安定して得られることや、顧客離反が少ないのが特徴と言われています。
音楽や映像の配信サービス、クラウドストレージサービスや家電の利用サービス、ソフトウェアやフィットネスクラブなど、今やさまざまな業界・業態で活用されています。
フリーミアムモデル
『フリー(Free)』と『プレミアム(Premium)』を合わせて作られた『フリーミアムモデル』とは、基本的な機能は無料(フリー)で提供し、上位機能を有料(プレミアム)で提供するビジネスモデルです。
かつては会員になると会員限定の特典が得られるといったものも多かったのですが、近年はゲームアプリや健康管理アプリなど、デジタルコンテンツに活用されていることが多い印象です。ダウンロードと基本機能は無料で、アプリ内に課金機能があるアプリは誰もが一度は見たことがあるのではないでしょうか。
基本機能は無料で使えるため、ユーザーの導入ハードルが低く、ユーザーを多く集めやすいという特徴があります。
まとめ
『ビジネスモデル』という言葉は一般的に使われるビジネス用語で手垢がついた印象ではありますが、市場の変化が目まぐるしい今だからこそ、自社のビジネスモデルを改めて見直すことも重要ですね。
近年、高速インターネットの普及などによってビジネスのグローバル化が一層加速しており、海外市場への展開や、海外からの人材活用を考える企業も増えています。
国をあげてDX化が推奨されているにもかかわらず、国内のIT人材不足は深刻で、優秀な人材を国内だけで探すのは難易度が高く、育成にもある程度の時間がかかります。
1970年代当初にはコスト削減を目的として利用されていたオフショア開発は、近年では優秀な人材を確保する方法の一つとして選択されることも増えてきました。海外に目を向ければ、開発をはじめ、ITに関する知識や経験が豊富な多くの人材に出会うことができます。
「オフショア開発. com」は、厳正な審査を通過した、オフショア開発企業が多数パートナーとなっております。オフショア開発、外国人材採用に関する専門スタッフが無料で御社のお悩みにお答えします。お悩み、ご相談などありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。