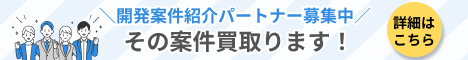最終更新日:2025/10/07
INDEX
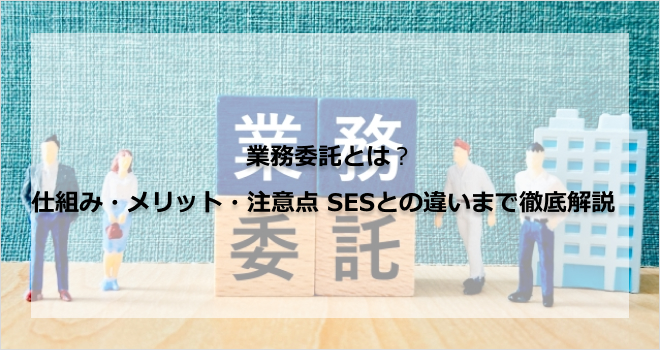
働き方の多様化が進み、多くの企業が人手不足に悩んでいる現代において、外部リソースを活用している、または活用を検討している企業は少なくありません。
「業務委託」は特定の業務を外部に任せる契約形態です。本記事では、業務委託の基本から他の契約形態との違い、メリット・デメリット、実務上の注意点まで詳しく解説します。
業務委託とは
実は法律上「業務委託契約」という名称の契約は存在せず、一般に、民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称して「業務委託契約」と呼んでいます。
業務委託では、委託者には受託者に対する指揮命令権がなく、受託者は自己の裁量と責任で業務を遂行します。業務の進め方や作業時間などは受託者が自ら決定し、委託者は具体的な業務指示を出すことができません。
請負契約では成果物の完成と引き換えに報酬が支払われ、委任・準委任契約では業務の遂行自体に対して報酬が発生します。
雇用契約・派遣契約との違い
業務委託を正しく理解するには、雇用契約や派遣契約との違いを明確に把握することが重要です。この項では雇用契約と派遣契約について解説します。
雇用契約
雇用契約は、労働者が使用者の指揮命令下で労働力を提供し、その対価として賃金を受け取る契約です。正社員や契約社員、アルバイトやパートなど、企業と直接結ぶ契約であり、従業員は会社の就業規則や指示に従って働く義務があります。
企業は給与を支給し、所得税や住民税を源泉徴収して納付する義務を負います。さらに、一定の条件を満たす労働者は社会保険や労働保険の適用対象となり、企業は保険料の一部を負担します。労働者は労働基準法などの保護を受け、最低賃金や労働時間、年次有給休暇などが保障されます。
派遣契約
派遣契約は、派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先企業で就業する契約形態です。派遣労働者の給与は派遣会社から支払われ、福利厚生も派遣会社のものが適用されますが、実際の業務指示は派遣先企業から受けます。
派遣先は労働者に対して業務のやり方や勤務時間などを指定し、社内ルールの遵守を求めることができます。社会保険や雇用保険などの労務管理は派遣会社が責任を負います。
請負、準委任、SESとの違い
業務委託契約は請負契約、委任契約、準委任契約の総称であることはすでに述べたとおりですが、委任契約は税理士や弁護士など法律行為を委託する際に使われる契約形態であり、多くの業務委託では請負契約か準委任契約が選択されます。
さらにIT業界では準委任契約の一種としてSES契約が広く活用されています。各契約の特徴と違いを詳しく解説します。
請負契約
請負契約は、受託者が仕事の完成を約束し、委託者がその成果物に対して報酬を支払う契約です。受託者は自らの責任と判断で業務を遂行し、約束した成果物を完成させる義務を負い、成果物に欠陥があれば契約不適合責任を問われます。
ちなみに以前「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、民法の改正によって責任の範囲が拡大されるなどして2020年4月1日から「契約不適合責任」に改められています。
システム開発における請負契約では、仕様書に定められた機能を持つシステムを納期までに完成させることが求められます。成果物が完成しなければ、原則として報酬を受け取ることはできません。アプリ開発やWebサイト制作などで多く採用される契約形態です。
また、開発においては、請負契約という契約形態で行う開発のこと、もしくは請負契約そのものを『請負開発』『請負型開発』と呼びます。請負開発についてはこちらの記事に詳しく解説していますのでご一読ください。
https://www.offshore-kaihatsu.com/contents/general/what-is-contract-development/
準委任契約
準委任契約では業務の遂行が契約の目的であり、成果物の完成義務はありません。コンサルタントによるアドバイスなど、それ自体は目に見える成果や直接的な結果につながらない業務に適用されます。たとえばシステムエンジニアが客先に常駐して技術支援を順委任契約によって行う場合、「月160時間の技術支援を提供する」ことが契約内容となり、特定のシステムを完成させることは求められません。
準委任契約は「履行割合型」と「成果完成型」に分類され、履行割合型は作業時間や工数に応じて報酬が支払われる契約で、月額固定の技術顧問契約などが例として挙げられます。成果完成型は調査報告書の提出など一定の成果物を前提としますが、完成責任や契約不適合責任は負いません。
SES契約
SES(システム・エンジニアリング・サービス)契約は準委任契約の一種であり、IT技術者の技術力を一定期間提供する契約です。
SES企業に雇用されたエンジニアはクライアント企業で業務を行いますが、指揮命令権はSES企業側にあります。クライアント企業はエンジニアに直接業務指示を出すことができません。
派遣契約と似ているように見えますが、指揮命令権の所在が正反対であることに注意が必要です。
業務委託のメリット
業務委託には多くのメリットがあります。ここでは「コスト調整」「ノウハウの活用」「社員がコア業務に専念可能」の3つのメリットを解説します。
①コスト調整
専門性の高い人材を短期間だけ必要とする場合には、正社員よりも業務委託の方がコストを抑えられます。
正社員を雇用すれば、繁閑に関わらず給与や社会保険料を支払い続ける必要がありますが、業務委託なら繁忙期のみの活用が可能で、採用コストや教育研修費、福利厚生費、オフィススペースや備品など多くのコストが削減できます。
②ノウハウの活用
最新のマーケティング手法、高度なプログラミング技術、専門的なデザインスキルなどを社内で育成するには時間とコストがかかりますが、外部の専門家に委託することで、自社の競争力を素早く維持・向上させることができます。教育投資を抑えながら、高品質な成果物を得られる点は業務委託の大きなメリットだと言えるでしょう。
③社員がコア業務に専念可能
専門性の低い業務などを外部委託することで、従業員の業務負担を減らし、付加価値の高い業務に集中させることができます。結果として組織全体の生産性が向上し、社員のモチベーション向上にもつながります。業務委託は限られた人的資源を最大限に活用するための有効な手段です。
業務委託のデメリット
業務委託にはメリットだけでなくデメリットも存在します。ここでは「ノウハウが蓄積できない」「情報漏洩のリスク」について解説します。
①ノウハウが蓄積できない
外部に業務を委託した場合、成果物は手に入りますが、それを作り出すプロセスや技術は得られないため、長期的に見ると自社の技術力や問題解決能力が向上しない可能性があります。
委託先との定期的な情報共有の機会を設け、作業プロセスや考え方を学ぶ仕組みを作ることが重要です。
②情報漏洩のリスク
業務委託では、社内の機密情報や個人情報を外部の受託者と共有することがあるため、受託者の管理体制によっては情報漏洩のリスクが高まります。特に受託者が再委託を行う場合には情報の管理がさらに難しくなることがあります。そのため、秘密保持契約(NDA)の締結は必須であり、再委託を行う場合の条件や制限も契約書に明記すべきです。
また、委託先の情報セキュリティ体制を事前に審査し、定期的な監査を行うことも重要です。
まとめ
業務委託は、請負契約、委任/準委任契約の総称で、企業が外部リソースを活用するための重要な手段です。システム開発において最適なパートナーを見つけることはプロジェクトの成否を左右する重要な要素ですが、近年、国内のIT人材は慢性的に不足しており、人件費も高騰しているため、人材探しにお悩みの企業は多く、解決策の一つとしてオフショア開発が検討されています。
オフショア開発.comでは専門コンシェルジュによる無料相談をご提供しています。ご相談から候補となるオフショア開発企業のご紹介まで、すべて無料でご利用いただけます。ご発注になった際の成約手数料もございませんので、安心してご利用ください。
- CMS費用のすべて|導入前に知るべき相場・内訳・節約ポイント
- 【PR】“社員が退職しない開発拠点「ベトナム・フエ」” 3年連続 離職率1%未満、株式会社ブライセンとは?
- システム開発の費用ガイド|相場の見方・見積り内訳とコストを抑える実践術
- Web開発会社選び|費用・品質・納期で失敗しない進め方
- システム開発外注ガイド|失敗しない選び方と進め方
- Xcode(エックスコード)とは?Xcodeで作れるアプリやメリット解説
- iOSアプリ開発とは|はじめてでもわかる流れと用語解説
- 開発工程とは|フェーズ別の流れとやることをわかりやすく解説
- アプリ開発を依頼するには?メリット・相場・選び方を徹底解説
- 結合テストとは?目的・種類・実施時のポイントを解説