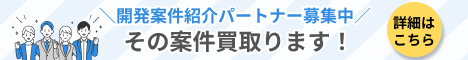最終更新日:2025/11/05
INDEX
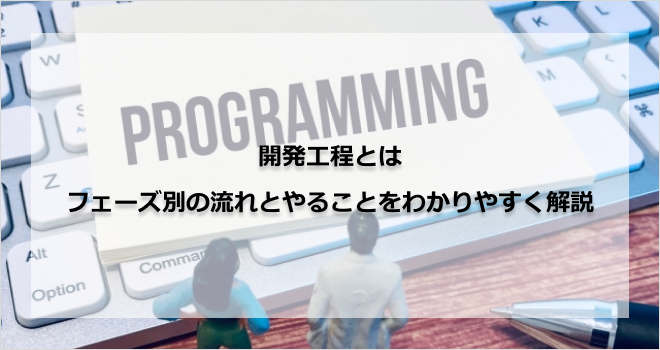
システム開発は、要件定義から運用・保守といったさまざまな工程を経て進められます。各工程には明確な目的と成果物があり、段階的に進めることで品質の高いシステムを構築できます。
本記事では、開発工程の基本的な流れと各フェーズの詳細、工程を分けることのメリット、そして開発現場でよく使われる専門用語について解説します。
システム開発工程
システム開発工程は、プロジェクトの規模や採用する開発手法によって異なりますが、一般的に上流工程と下流工程に大別されます。上流工程は要件定義から設計まで、下流工程は実装からリリース、運用・保守までを指します。
各工程を順序立てて進めることで、手戻りを最小限に抑え、効率的な開発が実現できます。
システム開発工程については以前、別の記事でも解説しましたが、下記の記事は具体的な流れや代表的な開発手法について解説しています。より深くシステム開発工程について知りたい方は合わせてご一読ください。
https://www.offshore-kaihatsu.com/contents/general/system-development-process/
プロジェクト計画
プロジェクト計画とは、開発プロジェクトを実行するための計画を策定する初期工程です。
計画段階では、プロジェクトのスコープや予算、スケジュールと必要な人的リソース、リスク管理、品質基準などを定義します。具体的な作業をタスクに分解し、順序立てて並べ、各タスクの開始・終了時期をスケジューリングします。
ここで立てた計画はプロジェクトを進行する上でのガイドラインとして機能し、常に見直しと調整が必要となります。
要件定義
要件定義とは重要な用件や必要な条件(要件)と、言葉の意味や用法についての共通認識を定めること(定義)を組み合わせた言葉であり、開発を実際に進めていく前にまず何をどのような手法で作っていくのかを決める工程です。
クライアントと開発担当との間で、要件に関する認識のずれがあると、出来上がったシステムが要望と異なるものとなり、大きなトラブルに発展しかねません。この工程では、お互いが認識をしっかり合わせておくことが重要です。
要件定義についてはこちらの記事も参考になります。
https://www.offshore-kaihatsu.com/contents/general/requirement
設計
設計には外部設計と内部設計があり、各機能がそれぞれ要件の実現に対して何をするのかを決めるのが外部設計(基本設計)です。システムが外側、つまりユーザーから見てどのような動きをするのかを設計する工程なので外部設計と呼ばれます。ここでは『基本設計書』を作成します。
内部設計(詳細設計)では、外部設計で決定した内容を実際にどう実現するかを設計します。ここでは機能の仕様やデータベースの設計、データの流れなどを記載した『詳細設計書』を作成します。内部、つまり開発側から見てわかるシステム設計を行う工程であるため、内部設計と言われます。
実装
実装とは、設計書に基づいてプログラムコードを記述し、システムを構築する工程です。システムの機能が具体的な形となるのがこの段階です。
テスト
システムが形になったとしても、まだ完成とは言えません。実際に意図通りの動きをするか、バグがないかなどを確認するのがテスト工程です。
テストには、モジュール単位でテストを確認する『単体テスト(ユニットテスト)』や、モジュール同士を組み合わせてテストを行う『結合テスト』、システム全体の動きを実際とほぼ同じ環境で確認する『総合テスト』、リリース前の最後のテストであり、ユーザーが使うことを想定して行う『運用テスト』などさまざまなテストがあります。
リリース
全てのテストが問題なく終わった段階で、システムをリリースする工程に移ります。古いシステムからの移行がある場合は切り替えを行います。切り替えには、機能ごとに段階を経て切り替える順次移行、全てを一気に切り替える一斉移行といった方法があります。
開発工程を分けるメリット
開発工程を分けることによって得られるメリットにはさまざまなものがありますが、ここでは2つのメリットについて解説します。
タスク管理
工程を分割することで、プロジェクト全体を管理可能な単位に分解でき、各タスクの進捗状況を可視化できます。システム開発は長期間に及ぶものも多いため、工程ごとにゴールを細かく設定することで管理もしやすくなります。
人員配置を最適化
工程を分けることによって、それぞれの段階で必要となる技能を明確にすることができ、最適な人材配置が可能になります。段階ごとに人員計画を行うことができれば、適切なタイミングで必要な人材を確保し、結果、コスト削減にもつながります。
開発工程でよく使われる用語(5選)
開発の現場では、専門用語が日常的に使われています。ここではよく使われる用語5選をご紹介します。
人月、人日
人月は「にんげつ」と読み、人日は「にんにち」と読みます。どちらも工数を表す単位であり、人月は1人で1ヶ月かかる作業量を1人月として計算するのに対し、人日は1人で1日かかる作業量を1人日として計算します。
10人のエンジニアで半年かかる作業量は10人×6ヶ月で60人月となり、5人のエンジニアで10日かかる作業量は5人×10日で50人日という計算です。
RFP
RFPとは「Request for Proposal」の頭文字を取った言葉で、開発を行う上での要望や、さまざまな要件を取りまとめて文書化した提案依頼書です。
RFPで発注元の要望を文書化することによって、要望が明確化され、コミュニケーションのずれを防ぐことができます。開発において発注元・発注先が共に満足のいく成果を出すためにもなくてはならない存在です。
RFPについては下記の記事に詳しく解説していますので、さらに理解を深めたい方はぜひご一読ください。
https://www.offshore-kaihatsu.com/contents/general/rfp
オープンソース
オープンソースとは、プログラムの設計図であるソースコードを無料で一般公開することです。利用者は自由に内容を確認し、変更を加え、配布することができます。オープンソースを活用することでライセンスにかかる費用を抑えることができますが、オープンソースにも一定の制約があるため、開発にあたっては注意が必要です。
デバッグ
デバッグとは、欠陥を指す「bug」に除去を意味する「de」がついた言葉であり、欠陥を除去することを指します。つまり、プログラムの誤りや不具合を見つけ出して修正する作業のことです。
ライブラリ
ライブラリとは、プログラミングの効率を上げるために、よく使われる処理をまとめて再利用できるようにしたもので、言うなればプログラムの部品集です。必要な機能だけを使うことができるため、多くの開発者が活用しています。
Androidアプリ開発に活用できるライブラリについては、以前下記の記事でもご紹介しましたので、こちらも参考になさってください。
https://www.offshore-kaihatsu.com/contents/general/android-development/
まとめ
開発は長期間に及ぶことも少なくないため、プロセスを計画的に分割することで、進捗の把握がしやすくなり、人材を効果的に活用することができます。
質の高い開発を行うためには、各段階の重要性を認識し、計画的に作業を進めることが欠かせません。
開発においては、信頼できる開発パートナーの選択も大切な要素です。オフショア開発.comでは、豊富な実績と専門知識を持つオフショア開発企業の選定をサポートし、プロジェクトの成功に向けた最適なマッチングを提供しています。また、専門コンシェルジュによる無料相談をご提供しています。ご相談からご紹介まで、すべて無料でご利用いただけます。ご発注になった際の成約手数料もございませんので、安心してご利用ください。
- おすすめのWebアプリケーションフレームワーク・ライブラリ10選
- データベースとは | 構築の目的・会社選定を解説
- CMS費用のすべて|導入前に知るべき相場・内訳・節約ポイント
- 【PR】“社員が退職しない開発拠点「ベトナム・フエ」” 3年連続 離職率1%未満、株式会社ブライセンとは?
- システム開発の費用ガイド|相場の見方・見積り内訳とコストを抑える実践術
- Web開発会社選び|費用・品質・納期で失敗しない進め方
- システム開発外注ガイド|失敗しない選び方と進め方
- Xcode(エックスコード)とは?Xcodeで作れるアプリやメリット解説
- iOSアプリ開発とは|はじめてでもわかる流れと用語解説
- 開発工程とは|フェーズ別の流れとやることをわかりやすく解説